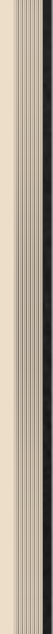








Seeds
あなたのNeedsとマッチしたタグです
- xPeerth運営
- xPeerthサービス提供
- x音響機器関連
- x音楽関連
- x普通自動車第一種運転
- xMacintosh関連
Needs
あなたのSeedsとマッチしたタグです
- x英語
- x中国語
- x映像編集
- x映像プロデュース
- xWEBデザイン
- xFlashデザイン
- xWEBプログラミング
- xアプリケーションエンジニアリング
- xWEBプランニング
- xWEBクリエイト
- CGデザイン
- WEBディレクション
- ネットワークプログラミング
- 楽器修理
- イラスト画
- 映画制作
- アニメ制作
- フラッシュ制作
- デジタル一眼レフカメラ撮影
- 殺陣
Phrase
あなたのPhraseとマッチしたタグです
- xPeerthCOO
- xPeerth運営
- xRecording_Eng
- xMusican
- xMacintosh_User
- キャサリンパーティー
- 2011超花見大会
※検索結果に表示される自己紹介です。
[Peerth STAFF]
頑張ってPeerthをなんとかしようとなんかしているアラサーです。
頑張ってPeerthをなんとかしようとなんかしているアラサーです。
フリースペース
胎児よ
胎児よ
何故躍る
母親の心がわかって
おそろしいのか
…………ブウウ――――――ンンン――――――ンンンン………………。
私がウスウスと眼を覚ました時、こうした蜜蜂みつばちの唸うなるような音は、まだ、その弾力の深い余韻を、私の耳の穴の中にハッキリと引き残していた。
それをジッと聞いているうちに……今は真夜中だ
な……と直覚した。そうしてどこか近くでボンボン時計が鳴っているんだな……と思い思い、又もウトウトしているうちに、その蜜蜂のうなりのような余韻は、いつとなく次々に消え薄れて行って、そこいら中がヒッソリと静まり返ってしまった。
私はフッと眼を開いた。
かなり高い、白ペンキ塗の天井裏から、薄白い塵埃に蔽われた裸の電球がタッタ一つブラ下がっている。その赤黄色く光る硝子球の横腹に、大きな蠅が一匹とまっていて、死んだように凝然としている。その真下の固い、冷めたい人造石の床の上に、私は大の字型に長くなって寝ているようである。
……おかしいな…………。
私は大の字型に凝然としたまま、瞼を一パイに見開いた。そうして眼の球だけをグルリグルリと上下左右に廻転さしてみた。
青黒い混凝土コンクリートの壁で囲まれた二間四方ばかりの部屋である。
その三方の壁に、黒い鉄格子と、鉄網で二重に張り詰めた、大きな縦長い磨硝子の窓が一つ宛、都合三つ取付けられている、トテも要心堅固に構えた部屋の感じである。
窓の無い側の壁の附け根には、やはり岩乗な鉄の寝台が一個、入口の方向を枕にして横たえてあるが、その上の真白な寝具が、キチンと敷き展べたままになっているところを見ると、まだ誰も寝たことがないらしい。
……おかしいぞ…………。
私は少し頭を持ち上げて、自分の身体を見廻わしてみた。
白い、新しいゴワゴワした木綿の着物が二枚重ねて着せてあって、短かいガーゼの帯が一本、胸高に結んである。そこから丸々と肥って突き出ている四本の手足は、全体にドス黒く、垢だらけになっている……そのキタナラシサ……。
……いよいよおかしい……。
怖わ怖わ右手をあげて、自分の顔を撫でまわしてみた。
……鼻が尖んがって……眼が落ち窪んで……頭髪が蓬々と乱れて……顎鬚がモジャモジャと延びて……。
……私はガバと跳ね起きた。
モウ一度、顔を撫でまわしてみた。
そこいらをキョロキョロと見廻わした。
……誰だろう……俺はコンナ人間を知らない……。
胸の動悸がみるみる高まった。早鐘を撞くように乱れ撃ち初めた……呼吸が、それに連れて荒くなった。やがて死ぬかと思うほど喘ぎ出した。……かと思うと又、ヒッソリと静まって来た。
……こんな不思議なことがあろうか……。
……自分で自分を忘れてしまっている……。
……いくら考えても、どこの何者だか思い出せない。……自分の過去の思い出としては、たった今聞いたブウ――ンンンというボンボン時計の音がタッタ一つ、記憶に残っている。……ソレッ切りである……。
……それでいて気は慥かである。森閑とした暗黒が、部屋の外を取巻いて、どこまでもどこまでも続き広がっていることがハッキリと感じられる……。
……夢ではない……たしかに夢では…………。
私は飛び上った。
……窓の前に駈け寄って、磨硝子の平面を覗いた。そこに映った自分の容貌を見て、何かの記憶を喚び起そうとした。……しかし、それは何にもならなかった。磨硝子の表面には、髪の毛のモジャモジャした悪鬼のような、私自身の影法師しか映らなかった。
私は身を飜して寝台の枕元に在る入口の扉に駈け寄った。鍵穴だけがポツンと開いている真鍮の金具に顔を近付けた。けれどもその金具の表面は、私の顔を写さなかった。只、黄色い薄暗い光りを反射するばかりであった。
……寝台の脚を探しまわった。寝具を引っくり返してみた。着ている着物までも帯を解いて裏返して見たけれども、私の名前は愚か、頭文字らしいものすら発見し得なかった。
私は呆然となった。私は依然として未知の世界に居る未知の私であった。私自身にも誰だかわからない私であった。
こう考えているうちに、私は、帯を引きずったまま、無限の空間を、ス――ッと垂直に、どこへか落ちて行くような気がしはじめた。臓腑の底から湧き出して来る戦慄と共に、我を忘れて大声をあげた。
それは金属性を帯びた、突拍子もない甲高い声であった……が……その声は私に、過去の何事かを思い出させる間もないうちに、四方のコンクリート壁に吸い込まれて、消え失せてしまった。
又叫んだ。……けれども矢張り無駄であった。その声が一しきり烈しく波動して、渦巻いて、消え去ったあとには、四つの壁と、三つの窓と、一つの扉が、いよいよ厳粛に静まり返っているばかりである。
又叫ぼうとした。……けれどもその声は、まだ声にならないうちに、咽喉の奥の方へ引返してしまった。叫ぶたんびに深まって行く静寂の恐ろしさ……。
奥歯がガチガチと音を立てはじめた。膝頭が自然とガクガクし出した。それでも自分自身が何者であったかを思い出し得ない……その息苦しさ。
私は、いつの間にか喘ぎ初めていた。叫ぼうにも叫ばれず、出ようにも出られぬ恐怖に包まれて、部屋の中央に棒立ちになったまま喘いでいた。
……ここは監獄か……精神病院か……。
そう思えば思うほど高まる呼吸の音が、凩のように深夜の四壁に反響するのを聞いていた。
そのうちに私は気が遠くなって来た。眼の前がズウ――と真暗くなって来た。そうして棒のように強直した全身に、生汗をビッショリと流したまま仰向け様にスト――ンと、倒れそうになったので、吾知らず観念の眼を閉じた……と思ったが……又、ハッと機械のように足を踏み直した。両眼をカッと見開いて、寝台の向側の混凝土壁を凝視した。
その混凝土壁の向側から、奇妙な声が聞えて来たからであった。
……それは確かに若い女の声と思われた。けれども、その音調はトテも人間の肉声とは思えないほど嗄れてしまって、ただ、底悲しい、痛々しい響ばかりが、混凝土の壁を透して来るのであった。
「……お兄さま。お兄さま。お兄さまお兄さまお兄さまお兄さまお兄さま。……モウ一度……今のお声を……聞かしてエ――ッ…………」
私は愕然として縮み上った。思わずモウ一度、背後を振り返った。この部屋の中に、私以外の人間が一人も居ない事を承知し抜いていながら……それから又も、その女の声を滲み透して来る、コンクリート壁の一部分を、穴のあく程、凝視した。
「……お兄さまお兄さまお兄さまお兄さまお兄さま……お隣りのお部屋に居らっしゃるお兄様……あたしです。妾です。お兄様の許嫁だった……貴方の未来の妻でした妾……あたしです。あたしです。どうぞ……どうぞ今のお声をモウ一度聞かして……聞かして頂戴……聞かして……聞かしてエ――ッ……お兄様お兄様お兄様お兄様……おにいさまア――ッ……」
私は眼瞼が痛くなるほど両眼を見開いた。唇をアングリと開いた。その声に吸い付けられるようにヒョロヒョロと二三歩前に出た。そうして両手で下腹をシッカリと押え付けた。そのまま一心に混凝土の壁を白眼み付けた。
それは聞いている者の心臓を虚空に吊るし上げる程のモノスゴイ純情の叫びであった。臓腑をドン底まで凍らせずには措かないくらいタマラナイ絶体絶命の声であった。……いつから私を呼び初めたかわからぬ……そうしてこれから先、何千年、何万年、呼び続けるかわからない真剣な、深い怨みの声であった。それが深夜の混凝土壁の向うから私? を呼びかけているのであった。
「……お兄さま……お兄さまお兄さまお兄さま。なぜ……なぜ返事をして下さらないのですか。あたしです、あたしです、あたしですあたしです。お兄さまはお忘れになったのですか。妾ですよ。あたしですよ。お兄様の許嫁だった……妾……妾をお忘れになったのですか。……妾はお兄様と御一緒になる前の晩に……結婚式を挙げる前の晩の真夜中に、お兄様のお手にかかって死んでしまったのです。……それがチャント生き返って……お墓の中から生き返ってここに居るのですよ。幽霊でも何でもありませんよ……お兄さまお兄さまお兄さまお兄さま。……ナゼ返事をして下さらないのですか……お兄様はあの時の事をお忘れになったのですか……」
私はヨロヨロと背後に蹌踉いた。モウ一度眼を皿のようにしてその声の聞こえて来る方向を凝視した……。
……何という奇怪な言葉だ。
……壁の向うの少女は私を知っている。私の許嫁だと云っている。……しかも私と結婚式を挙げる前の晩に、私の手にかかって殺された……そうして又、生き返った女だと自分自身で云っている。そうして私と壁一重を隔てた向うの部屋に閉じ籠められたまま、ああして夜となく、昼となく、私を呼びかけているらしい。想像も及ばない怪奇な事実を叫びつづけながら、私の過去の記憶を喚び起すべく、死物狂いに努力し続けているらしい。
……キチガイだろうか。
……本気だろうか。
いやいや。キチガイだキチガイだ……そんな馬鹿な……不思議な事が……アハハハ……。
私は思わず笑いかけたが、その笑いは私の顔面筋肉に凍り付いたまま動かなくなった。……又も一層悲痛な、深刻な声が、混凝土の壁を貫いて来たのだ。笑うにも笑えない……たしかに私を私と知っている確信にみちみちた……真剣な……悽愴とした……。
「……お兄さまお兄さまお兄さま。何故、御返事をなさらないのですか。妾がこんなに苦しんでいるのに……タッタ一言……タッタ一言……御返事を……」
「……………………」
「……タッタ一言……タッタ一言……御返事をして下されば……いいのです。……そうすればこの病院のお医者様に、妾がキチガイでない事が……わかるのです。そうして……お兄様も妾の声が、おわかりになるようになった事が、院長さんにわかって……御一緒に退院出来るのに………お兄様お兄様お兄様お兄さま……何故……御返事をして下さらないのですか……」
「……………………」
「……妾の苦しみが、おわかりにならないのですか……毎日毎日……毎夜毎夜、こうしてお呼びしている声が、お兄様のお耳に這入らないのですか……ああ……お兄様お兄様お兄様お兄様……あんまりです、あんまりですあんまりです……あ……あ……あたしは……声がもう……」
そう云ううちに壁の向側から、モウ一つ別の新しい物音が聞え初めた。それは平手か、コブシかわからないが、とにかく生身の柔らかい手で、コンクリートの壁をポトポトとたたく音であった。皮膚が破れ、肉が裂けても構わない意気組で叩き続ける弱々しい女の手の音であった。私はその壁の向うに飛び散り、粘り付いているであろう血の痕跡を想像しながら、なおも一心に眼を瞠り、奥歯を噛み締めていた。
「……お兄様お兄様お兄様お兄様……お兄様のお手にかかって死んだあたしです。そうして生き返っている妾です。お兄様よりほかにお便たよりする方は一人もない可哀想な妹です。一人ポッチでここに居る……お兄様は妾をお忘れになったのですか……」
「お兄様もおんなじです。世界中にタッタ二人の妾たちがここに居るのです。そうして他人からキチガイと思われて、この病院に離れ離れになって閉じ籠められているのです」
「……………………」
「お兄様が返事をして下されば……妾の云う事がホントの事になるのです。妾を思い出して下されば、妾も……お兄様も、精神病患者でない事がわかるのです……タッタ一言……タッタ一コト……御返事をして下されば……モヨコと……妾の名前を呼んで下されば……ああ……お兄様お兄様お兄様お兄様お兄様……ああ……妾は、もう声が……眼が……眼が暗くなって……」
私は思わず寝台の上に飛乗った。その声のあたりと思われる青黒い混凝土壁に縋り付いた。すぐにも返事をしてやりたい……少女の苦しみを助けてやりたい……そうして私自身がどこの何者かという事実を一刻も早く確かめたいという、タマラナイ衝動に駆られてそうしたのであった。……が……又グット唾液を嚥んで思い止まった。
胎児よ
何故躍る
母親の心がわかって
おそろしいのか
…………ブウウ――――――ンンン――――――ンンンン………………。
私がウスウスと眼を覚ました時、こうした蜜蜂みつばちの唸うなるような音は、まだ、その弾力の深い余韻を、私の耳の穴の中にハッキリと引き残していた。
それをジッと聞いているうちに……今は真夜中だ
な……と直覚した。そうしてどこか近くでボンボン時計が鳴っているんだな……と思い思い、又もウトウトしているうちに、その蜜蜂のうなりのような余韻は、いつとなく次々に消え薄れて行って、そこいら中がヒッソリと静まり返ってしまった。
私はフッと眼を開いた。
かなり高い、白ペンキ塗の天井裏から、薄白い塵埃に蔽われた裸の電球がタッタ一つブラ下がっている。その赤黄色く光る硝子球の横腹に、大きな蠅が一匹とまっていて、死んだように凝然としている。その真下の固い、冷めたい人造石の床の上に、私は大の字型に長くなって寝ているようである。
……おかしいな…………。
私は大の字型に凝然としたまま、瞼を一パイに見開いた。そうして眼の球だけをグルリグルリと上下左右に廻転さしてみた。
青黒い混凝土コンクリートの壁で囲まれた二間四方ばかりの部屋である。
その三方の壁に、黒い鉄格子と、鉄網で二重に張り詰めた、大きな縦長い磨硝子の窓が一つ宛、都合三つ取付けられている、トテも要心堅固に構えた部屋の感じである。
窓の無い側の壁の附け根には、やはり岩乗な鉄の寝台が一個、入口の方向を枕にして横たえてあるが、その上の真白な寝具が、キチンと敷き展べたままになっているところを見ると、まだ誰も寝たことがないらしい。
……おかしいぞ…………。
私は少し頭を持ち上げて、自分の身体を見廻わしてみた。
白い、新しいゴワゴワした木綿の着物が二枚重ねて着せてあって、短かいガーゼの帯が一本、胸高に結んである。そこから丸々と肥って突き出ている四本の手足は、全体にドス黒く、垢だらけになっている……そのキタナラシサ……。
……いよいよおかしい……。
怖わ怖わ右手をあげて、自分の顔を撫でまわしてみた。
……鼻が尖んがって……眼が落ち窪んで……頭髪が蓬々と乱れて……顎鬚がモジャモジャと延びて……。
……私はガバと跳ね起きた。
モウ一度、顔を撫でまわしてみた。
そこいらをキョロキョロと見廻わした。
……誰だろう……俺はコンナ人間を知らない……。
胸の動悸がみるみる高まった。早鐘を撞くように乱れ撃ち初めた……呼吸が、それに連れて荒くなった。やがて死ぬかと思うほど喘ぎ出した。……かと思うと又、ヒッソリと静まって来た。
……こんな不思議なことがあろうか……。
……自分で自分を忘れてしまっている……。
……いくら考えても、どこの何者だか思い出せない。……自分の過去の思い出としては、たった今聞いたブウ――ンンンというボンボン時計の音がタッタ一つ、記憶に残っている。……ソレッ切りである……。
……それでいて気は慥かである。森閑とした暗黒が、部屋の外を取巻いて、どこまでもどこまでも続き広がっていることがハッキリと感じられる……。
……夢ではない……たしかに夢では…………。
私は飛び上った。
……窓の前に駈け寄って、磨硝子の平面を覗いた。そこに映った自分の容貌を見て、何かの記憶を喚び起そうとした。……しかし、それは何にもならなかった。磨硝子の表面には、髪の毛のモジャモジャした悪鬼のような、私自身の影法師しか映らなかった。
私は身を飜して寝台の枕元に在る入口の扉に駈け寄った。鍵穴だけがポツンと開いている真鍮の金具に顔を近付けた。けれどもその金具の表面は、私の顔を写さなかった。只、黄色い薄暗い光りを反射するばかりであった。
……寝台の脚を探しまわった。寝具を引っくり返してみた。着ている着物までも帯を解いて裏返して見たけれども、私の名前は愚か、頭文字らしいものすら発見し得なかった。
私は呆然となった。私は依然として未知の世界に居る未知の私であった。私自身にも誰だかわからない私であった。
こう考えているうちに、私は、帯を引きずったまま、無限の空間を、ス――ッと垂直に、どこへか落ちて行くような気がしはじめた。臓腑の底から湧き出して来る戦慄と共に、我を忘れて大声をあげた。
それは金属性を帯びた、突拍子もない甲高い声であった……が……その声は私に、過去の何事かを思い出させる間もないうちに、四方のコンクリート壁に吸い込まれて、消え失せてしまった。
又叫んだ。……けれども矢張り無駄であった。その声が一しきり烈しく波動して、渦巻いて、消え去ったあとには、四つの壁と、三つの窓と、一つの扉が、いよいよ厳粛に静まり返っているばかりである。
又叫ぼうとした。……けれどもその声は、まだ声にならないうちに、咽喉の奥の方へ引返してしまった。叫ぶたんびに深まって行く静寂の恐ろしさ……。
奥歯がガチガチと音を立てはじめた。膝頭が自然とガクガクし出した。それでも自分自身が何者であったかを思い出し得ない……その息苦しさ。
私は、いつの間にか喘ぎ初めていた。叫ぼうにも叫ばれず、出ようにも出られぬ恐怖に包まれて、部屋の中央に棒立ちになったまま喘いでいた。
……ここは監獄か……精神病院か……。
そう思えば思うほど高まる呼吸の音が、凩のように深夜の四壁に反響するのを聞いていた。
そのうちに私は気が遠くなって来た。眼の前がズウ――と真暗くなって来た。そうして棒のように強直した全身に、生汗をビッショリと流したまま仰向け様にスト――ンと、倒れそうになったので、吾知らず観念の眼を閉じた……と思ったが……又、ハッと機械のように足を踏み直した。両眼をカッと見開いて、寝台の向側の混凝土壁を凝視した。
その混凝土壁の向側から、奇妙な声が聞えて来たからであった。
……それは確かに若い女の声と思われた。けれども、その音調はトテも人間の肉声とは思えないほど嗄れてしまって、ただ、底悲しい、痛々しい響ばかりが、混凝土の壁を透して来るのであった。
「……お兄さま。お兄さま。お兄さまお兄さまお兄さまお兄さまお兄さま。……モウ一度……今のお声を……聞かしてエ――ッ…………」
私は愕然として縮み上った。思わずモウ一度、背後を振り返った。この部屋の中に、私以外の人間が一人も居ない事を承知し抜いていながら……それから又も、その女の声を滲み透して来る、コンクリート壁の一部分を、穴のあく程、凝視した。
「……お兄さまお兄さまお兄さまお兄さまお兄さま……お隣りのお部屋に居らっしゃるお兄様……あたしです。妾です。お兄様の許嫁だった……貴方の未来の妻でした妾……あたしです。あたしです。どうぞ……どうぞ今のお声をモウ一度聞かして……聞かして頂戴……聞かして……聞かしてエ――ッ……お兄様お兄様お兄様お兄様……おにいさまア――ッ……」
私は眼瞼が痛くなるほど両眼を見開いた。唇をアングリと開いた。その声に吸い付けられるようにヒョロヒョロと二三歩前に出た。そうして両手で下腹をシッカリと押え付けた。そのまま一心に混凝土の壁を白眼み付けた。
それは聞いている者の心臓を虚空に吊るし上げる程のモノスゴイ純情の叫びであった。臓腑をドン底まで凍らせずには措かないくらいタマラナイ絶体絶命の声であった。……いつから私を呼び初めたかわからぬ……そうしてこれから先、何千年、何万年、呼び続けるかわからない真剣な、深い怨みの声であった。それが深夜の混凝土壁の向うから私? を呼びかけているのであった。
「……お兄さま……お兄さまお兄さまお兄さま。なぜ……なぜ返事をして下さらないのですか。あたしです、あたしです、あたしですあたしです。お兄さまはお忘れになったのですか。妾ですよ。あたしですよ。お兄様の許嫁だった……妾……妾をお忘れになったのですか。……妾はお兄様と御一緒になる前の晩に……結婚式を挙げる前の晩の真夜中に、お兄様のお手にかかって死んでしまったのです。……それがチャント生き返って……お墓の中から生き返ってここに居るのですよ。幽霊でも何でもありませんよ……お兄さまお兄さまお兄さまお兄さま。……ナゼ返事をして下さらないのですか……お兄様はあの時の事をお忘れになったのですか……」
私はヨロヨロと背後に蹌踉いた。モウ一度眼を皿のようにしてその声の聞こえて来る方向を凝視した……。
……何という奇怪な言葉だ。
……壁の向うの少女は私を知っている。私の許嫁だと云っている。……しかも私と結婚式を挙げる前の晩に、私の手にかかって殺された……そうして又、生き返った女だと自分自身で云っている。そうして私と壁一重を隔てた向うの部屋に閉じ籠められたまま、ああして夜となく、昼となく、私を呼びかけているらしい。想像も及ばない怪奇な事実を叫びつづけながら、私の過去の記憶を喚び起すべく、死物狂いに努力し続けているらしい。
……キチガイだろうか。
……本気だろうか。
いやいや。キチガイだキチガイだ……そんな馬鹿な……不思議な事が……アハハハ……。
私は思わず笑いかけたが、その笑いは私の顔面筋肉に凍り付いたまま動かなくなった。……又も一層悲痛な、深刻な声が、混凝土の壁を貫いて来たのだ。笑うにも笑えない……たしかに私を私と知っている確信にみちみちた……真剣な……悽愴とした……。
「……お兄さまお兄さまお兄さま。何故、御返事をなさらないのですか。妾がこんなに苦しんでいるのに……タッタ一言……タッタ一言……御返事を……」
「……………………」
「……タッタ一言……タッタ一言……御返事をして下されば……いいのです。……そうすればこの病院のお医者様に、妾がキチガイでない事が……わかるのです。そうして……お兄様も妾の声が、おわかりになるようになった事が、院長さんにわかって……御一緒に退院出来るのに………お兄様お兄様お兄様お兄さま……何故……御返事をして下さらないのですか……」
「……………………」
「……妾の苦しみが、おわかりにならないのですか……毎日毎日……毎夜毎夜、こうしてお呼びしている声が、お兄様のお耳に這入らないのですか……ああ……お兄様お兄様お兄様お兄様……あんまりです、あんまりですあんまりです……あ……あ……あたしは……声がもう……」
そう云ううちに壁の向側から、モウ一つ別の新しい物音が聞え初めた。それは平手か、コブシかわからないが、とにかく生身の柔らかい手で、コンクリートの壁をポトポトとたたく音であった。皮膚が破れ、肉が裂けても構わない意気組で叩き続ける弱々しい女の手の音であった。私はその壁の向うに飛び散り、粘り付いているであろう血の痕跡を想像しながら、なおも一心に眼を瞠り、奥歯を噛み締めていた。
「……お兄様お兄様お兄様お兄様……お兄様のお手にかかって死んだあたしです。そうして生き返っている妾です。お兄様よりほかにお便たよりする方は一人もない可哀想な妹です。一人ポッチでここに居る……お兄様は妾をお忘れになったのですか……」
「お兄様もおんなじです。世界中にタッタ二人の妾たちがここに居るのです。そうして他人からキチガイと思われて、この病院に離れ離れになって閉じ籠められているのです」
「……………………」
「お兄様が返事をして下されば……妾の云う事がホントの事になるのです。妾を思い出して下されば、妾も……お兄様も、精神病患者でない事がわかるのです……タッタ一言……タッタ一コト……御返事をして下されば……モヨコと……妾の名前を呼んで下されば……ああ……お兄様お兄様お兄様お兄様お兄様……ああ……妾は、もう声が……眼が……眼が暗くなって……」
私は思わず寝台の上に飛乗った。その声のあたりと思われる青黒い混凝土壁に縋り付いた。すぐにも返事をしてやりたい……少女の苦しみを助けてやりたい……そうして私自身がどこの何者かという事実を一刻も早く確かめたいという、タマラナイ衝動に駆られてそうしたのであった。……が……又グット唾液を嚥んで思い止まった。







